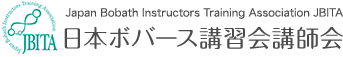第41回 International Bobath Instructors Training Association Congress の教育講演では、以下の3名の先生方にご講演いただくことになりました。本講演は会員外の方でもオンデマンド配信でご視聴いただくことが可能ですので、この機会にぜひお申し込みください。
*本講演は英語でのプレゼンテーションとなっております。
高草木 薫 先生(旭川医科大学)
高草木先生は、運動制御や姿勢制御に関する研究を行っておられます。特に、姿勢制御メカニズムや運動学習に焦点を当て、私たちに非常に有用な情報を提供していただいております。
内藤 栄一 先生(脳情報通信融合研究センター)
内藤先生は、人間の感覚・運動機能の理解とその改善・向上に関する研究を行っておられます。主な研究テーマは、身体像、身体意識や自己意識の脳内表現、運動イメージ、運動適応、感覚運動連関など多岐にわたります。
山崎 弘嗣 先生(埼玉県立大学)
山崎先生は、運動の質的分析に関する研究を行っておられます。具体的には、運動パフォーマンスの向上やリハビリテーションにおける運動評価の質的手法に焦点を当て、臨床現場での応用を目指した研究を進めておられます。
各分野において豊富な知識と経験をお持ちの先生方による講演は、参加者の皆様にとって貴重な学びの機会となることでしょう。以下に、講演の要旨をご紹介いたします。
講演概要
Postural Control:姿勢制御
高草木 薫 先生 旭川医科大学
本講演では、姿勢制御に関わる神経機構について概説する。臨床研究により、姿勢・歩行障害は神経系全体および筋骨格系の機能不全に起因することが示されている。大脳皮質、基底核、小脳、脳幹、脊髄は、運動指令の遠心性コピーと多感覚フィードバックを時間的・空間的に統合・調整する。これにより、随意運動の多様なレパートリーは、予測的および反応的姿勢調整と結びつき、目的志向的な歩行活動を支持し、安定化させるための枠組みが形成される。
神経系の冗長性は、報酬志向型および誤差学習型の学習プロセスを介して、それぞれ基底核経路および小脳経路による適応や代償を可能にする。しかし、これらのシステムが障害されると、適応能力が損なわれ、不適応な変化を引き起こし、姿勢・歩行制御が障害される可能性がある。こうした障害が生じた場合、転倒のリスクが著しく増加するため、罹患率を低減するための介入が求められる。
本講演では、1) 脳幹および脊髄における基本的な姿勢制御システム、2) それらの活動を調節する神経伝達物質の役割、3) 大脳皮質、基底核、小脳による高次姿勢制御機能について概説する。最後に、これらの神経機構に基づいて、パーキンソン病における姿勢・歩行障害の病態生理について考察する。
Proprioceptive Neurorehabilitation
内藤 栄一 先生 脳情報通信融合研究センター
固有受容感覚は、人の運動制御や運動学習にとって極めて重要な役割を果たすだけでなく、身体図式の知覚を通した身体的自己意識の基盤である。本講演は、四肢の腱への振動刺激によって惹起される運動錯覚現象に焦点をあて、筋紡錘からの運動感覚信号が第一次運動野を中心とした運動領野ネットワークで処理されて、右半球下頭頂-前頭ネットワークの活性化によって意識に上る過程の基礎的知見を解説する。さらに、臨床に関連する以下の知見も紹介し、議論する。(1)運動錯覚の神経基盤である筋と運動野が形成する回路は、筋への振動刺激が手の痙縮や拘縮を軽減できる回路と共通していること、(2)自分の手が動いているという運動錯覚中の一人称的な感覚体験は、脳卒中後の運動機能回復を促進できること、最後に、(3)運動野や右半球下頭頂葉の運動意図と運動感覚の統合機能を活用したBilateral proprioceptive-motor couplingによる運動機能再建法の有効性も紹介する。
質的動作分析(Qualitative Movement Analysis:QMA): リハビリテーション専門家のための新しい視点
山崎 弘嗣 先生 埼玉県立大学
運動分析は、リハビリテーションにおいて中心的な役割を担っており、特に運動生成の根底にある適応戦略の理解を通じて、専門職が患者の運動機能を的確に把握することを可能にする。
従来の臨床評価は主に数値指標に依存して運動パフォーマンスを評価してきたが、これらの指標では、運動の構成要素における「連続性」「流動性」「秩序性」といった質的側面を捉えることが困難である。
質的運動分析(Qualitative Movement Analysis: QMA)は、個々の身体部位の個別機能ではなく、運動の構造的および関係的側面に着目することで、従来とは異なる視座を提供する。
このアプローチにより、治療介入に対する個別の応答を示唆する微細な運動パターンの変化を捉えることが可能となり、従来の評価方法では捉えにくかった新たな知見を導くことができる。
本講演では、運動の質を分析し、治療ターゲットを精緻化するための枠組みとしてQMAを紹介する。主なトピックは以下のとおりである。
- Body Members Concept:運動を構造化された機能システムとして捉える視点
- Optimization Principles:運動の質を、回復モニタリングの動的な指標として活用する方法
さらに、マーカーレスモーションキャプチャを活用した、現場で即時に使用可能な分析手法を紹介し、QMAを実際の臨床場面に応用するための具体的な方法を提示する。
本講演の目的は、臨床家に対して、運動行動の有意義な変化を「記述」「解釈」「導く」ための新たな言語的・概念的ツールを提供することにある。
(学会準備委員会翻訳)
ご視聴までの流れ
- 下記の申し込みページよりお申し込みください。
- 同ページ内よりクレジットカードにて決済をお願いします。
- 9月1日頃視聴用URLをメール(英語)にてお知らせいたします。視聴期限は9月末日までとなります。
申し込みフォーム
お申し込みはIBITA 2025 Tokyoのサイトにある申し込フォームからお願いします。
注意事項
- 支払いはクレジットカードのみとなります。
- 視聴にかかる通信費等はご負担ください。
- 複数人での視聴はご遠慮ください。
- 視聴用URLの譲渡・転送は厳禁です。